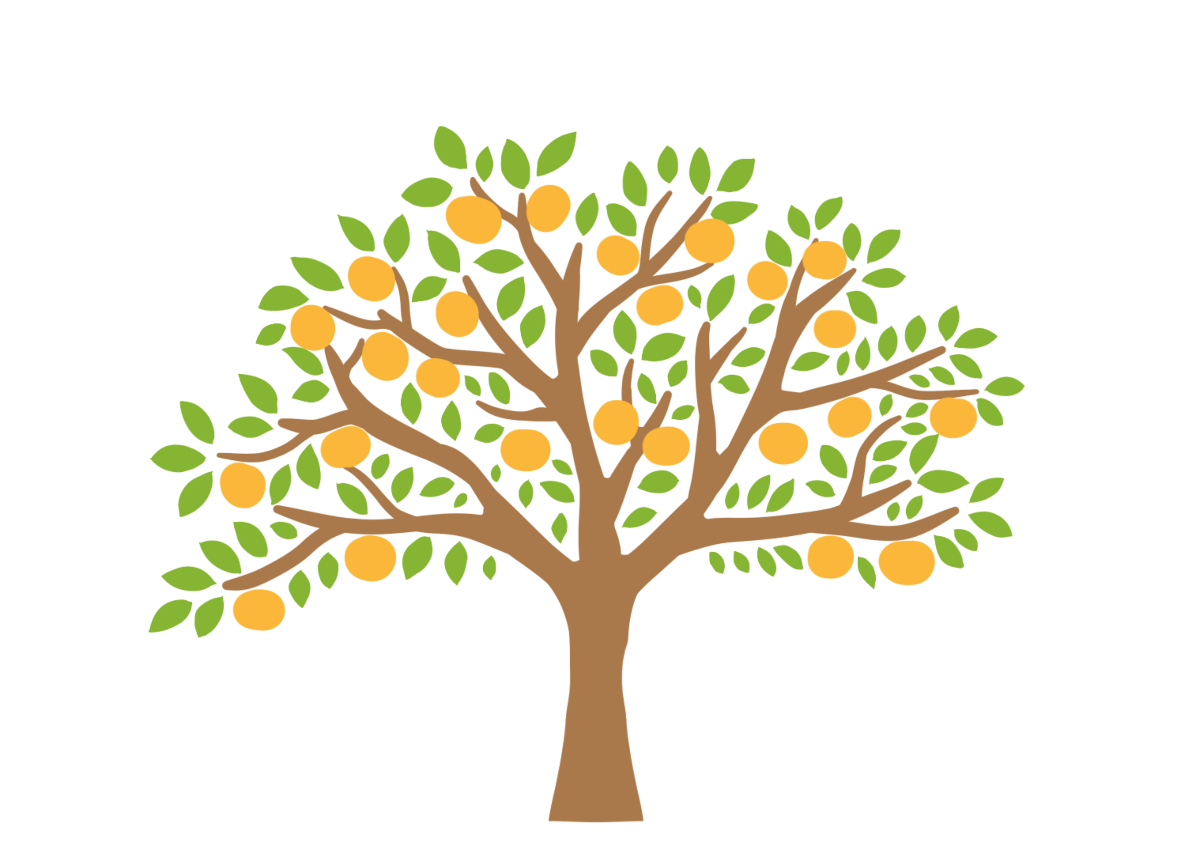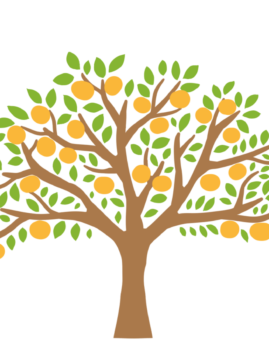寒冷地で柑橘類を栽培する際のポイントは、当たり前ですが耐寒性のある品種を選ぶことです。栽培地の最低気温を確認し、それに耐えられる品種を選ぶ必要があります。
鉢植えならば冬は室内に避難すれば済みますが、今回は畑に地植えしても越冬できる品種を探します。
また、冬場の管理も大切です。寒さを避けるための雪寒布の設置や、根の凍結を防ぐための根囲いの施工など、寒冷地ならではの対策が必要です。冬場の柑橘類の管理方法についても、今後、実際に試しながら調べて記事に反映させたいと考えています。
うちの畑の標高は750m
栽培を行う畑は、山梨県の山間部で標高約750mです。この地域の厳冬期の最低気温はマイナス10度以下になることもありますが、最近は温暖化の影響でそこまで下がる日は一冬に数日くらいです。雪はそれほど積もりません。山間地域なので強い冬型になると強風にのって風花が舞うときもあります。
周辺の畑では耐寒性の強い”柚子”の木が植えられています。柚子はこの気温でも越冬できていることから、柚子と同程度の耐寒性がある柑橘類であれば、この地での栽培が可能だと思います。
耐寒性のある柑橘類を調べる
柑橘類の耐寒性について検索したところ下のような研究を見つけました。
2016年の低温による被害から見たカンキツの耐凍性の品種間差異 / 松本和紀・奥村 麗・四宮 亮・村本晃司 / 福岡県農林業総合試験場研究報告 4(2018)pdfファイル
要約
2016年1月に九州地方で記録的な低温が続き、多くのカンキツ品種が凍害を受けた。朝倉市の調査圃場では38品種中35品種で葉や枝の凍害が見られた。葉枯れ指数と枝枯れ指数から品種の耐凍性を評価し、強から弱までランク分けできる。交雑親の耐凍性が子の耐凍性に影響し、耐凍性の強い親の子は強く、弱い親の子は弱い傾向がある。しかし、交雑組合せによっては耐凍性に幅が生じる。凍害後の回復力にも品種差があり、耐凍性と回復力は必ずしも一致しない。
この研究報告から耐凍性が最も強いと判断された品種を10品種挙げてみます。
1年生苗の寒害被害の少なかったもの上位10品種
- ユズ
- ジャバラ
- 清見
- スイートスプリング
- シークワーサー
- 日南1号
- させぼ温州
- 宮川早生
- 南津海
- はれひめ
ユズ、ジャバラ、シークワーサーはみかんのようにそのままでは食べれない柑橘類なので、この3種を除いた7品種が候補になりそうです。
寒冷地での柑橘系果樹栽培の基本
品種選びの前に寒冷地での柑橘類の栽培に関する基本をおさらいします。
土壌の選び方と準備
寒冷地では植え付け初期の生育がポイントになります。
まず、水はけがよく、深さ30cm以上の土壌が適しています。これにより、根の伸長と水分の供給が良好に保たれます。次に、土壌pHは5.5~7.0の範囲が好ましいとされています。酸性の土壌の場合は、苦土石灰を施用して pH を調整する必要があります。さらに、土壌が硬い場合は、深く掘り返して軟らかくし、腐葉土やバーク堆肥を混ぜ込むことで、水はけを改善することができます。
このように、適切な土壌条件を整えることが、寒冷地での柑橘系果樹栽培の成功につながるのです。
最適な植樹時期
柑橘類は春から初夏にかけての時期が適しています。この時期は気温が高く乾燥しにくいため、根の活着が良好になります。1年目の冬を迎えるまでに、健康で大きく育てたいところです。
日照条件の重要性
柑橘類は日当たりのよい場所を好みます。西日が強く当たりすぎないよう、北風も直接当たらない場所を選ぶことが大切です。また、成長スペースも十分に確保する必要があります。適切な日照条件を確保することで、柑橘類の健全な生育を維持することができます。
耐寒性のある柑橘系果樹の苗がインターネットで買えるか調べてみた。
ユズ、ジャバラ、シークワーサーはみかんのようにそのままでは食べれない柑橘類ので除外して、他の7品種についてネットで販売されているか調べて見ました。
清見
みかん類とオレンジ類の交配種です。以前静岡産のを食べましたが、とても美味しかった記憶があります。
収穫時期は2月中旬~3月上旬です。
この地域の最も寒い時期である12月~1月を実を成らせたまま越さなければならないので、おそらく実が凍ってしまうのではないでしょうか。私の住む地域では栽培は無理そうです。
清見オレンジは温州みかんとトロビタオレンジの交配品種で、1949年に日本で初めて作出された国産のタンゴール類。
果実は扁球形で温州みかんよりも大きく、200-250グラム程度の大きさがあります。皮はオレンジに似ていますが、オレンジよりはむきやすく、果肉にはほとんど種子がありません。果汁が豊富でとてもジューシー。甘さと酸味のバランスが良く、さわやかな甘みと香りが特徴です。
花は5月に咲き、小輪の白い花をつけます。樹形は常緑の高木で、最終的には地植えで2-2.5メートル、鉢植えで1-2メートル程度に成長します。
栽培は日当たりの良い場所であれば関東から九州まで可能です。初心者でも育てやすい耐病性・耐寒性のある品種です。小果実ながら1本ですでに実がなるため、家庭果樹としても人気があります。
スイートスプリング
スイートスプリングはハッサクとみかん類の交配種。収穫時期は、11月初旬頃から年明けの1月頃までなので、厳冬期前に収穫できそうです。
スイートスプリングは、1982年に静岡県の果樹試験場で「上田温州」と「はっさく」を交配して作出された、タンゼロ類の希少な柑橘品種です。
果実は200-250グラムと小ぶりで、表面の果皮はオレンジ色で厚めでゴツゴツしています。見た目はすっぱそうですが、実際には驚くほど甘く、はっさくのような苦みはありません。糖度は10-13度と高くありませんが、酸味が少なく、すっきりとした上品な甘さが特徴です。果汁も豊富でジューシーな味わいです。
花は5月に開花し、小輪の白い香り高い花をつけます。樹高は2-2.5メートルと低木で、日当たりのよい場所なら関東から九州まで栽培可能です。1本で実がなるので家庭果樹に適しています。
ただし、3センチほどのトゲがあるため、栽培には注意が必要です。トゲでけがをしないよう手入れ時は保護手袋を着用することをおすすめします。
日南1号
温州みかんの極早生品種。極早生9月中旬に収穫できます。樹勢が強く丈夫で育てやすいのが特徴です。
日南1号は、1979年に宮崎県日南市の野田明夫氏によって育成された温州みかんのです。
9月中旬に収穫できる極早生で、樹勢が強く丈夫なのが大きな特徴です。初心者でも育てやすい丈夫な品種といえます。
果実は表面が滑らかで、完熟時には濃いオレンジ色に変化します。糖度は9月下旬に10度、11月には11度を超え、高品質な甘みを得られます。果実の甘みをさらに高めるため、樹の根元に透湿性シートを敷いたマルチ栽培が効果的とされています。
5月に開花する小輪の白い花をつけ、1本ですでに結実します。北関東から九州の日当たりの良い場所で栽培可能です。
クエン酸が豊富なため残暑にぴったり。極早生で糖度の高い温州みかんを楽しみたい方におすすめの品種です。
させぼ温州
果実は厳冬期前の11月下旬から12月中旬に収穫できる温州みかんです。
宮川の枝変わりとして長崎で発見された温州みかんの中生品種です。
- 1本で結実するため、育てやすい品種です。
- 耐寒性があるので、関東から九州の日当たりの良い場所で栽培可能です。
- 果実は11月下旬から12月中旬に収穫できます。
- 果皮は剥きやすく、果汁が多いのが特徴です。
- 糖度は10-12度と高めで、甘みがあります。
- 宮川早生よりも果実は扁平で、濃いオレンジ色をしています。
- 葉数が多く、葉色も濃いため樹勢が強いのが特徴です。
- 耐寒性があり、日当たりの良い場所なら楽に栽培できるので、庭植えに向いています。
宮川早生
10月中旬に収穫できる早生品種です。
- 果実は10月中旬頃に収穫。果重140g、糖度10度程度。種はない。
- トゲがなく、耐寒性が強い。関東から九州まで栽培できる。
- 2-3年で結実。1本でも実がなる。樹高2-2.5m、葉張り2-3m。
- 耐寒性、耐暑性に優れ、初心者でも育てやすい品種。鉢植えには不向き。
南津海(なつみ)
5月に開花し約1年後の4月から5月にかけて収穫するタイプです。実をつけたまま越冬することになるので、この地域では無理そうです。
- 1978年に「カラーマンダリン」と「吉浦ポンカン」を交配して作出された。
- 果実は温州みかんより一回り大きい180-200グラム。表面はデコボコしており、オレンジ色です。
- 1年間樹上で熟成させるので、他の柑橘類よりも味わいが濃厚。糖度は13-14度と高いのが特徴。
- 種は若干入りますが、香り高く甘みが強い味わいで人気がある品種です。
- 樹勢が強く、毎年豊作。単為結果なので1本でも実がなります。
- 日当たりの良い場所なら関東から九州まで栽培可能。育てやすい品種です。
- 初夏に国産の高糖度柑橘を味わいたい方におすすめの一品です。
はれひめ
12月上旬頃に収穫できるようなので、有力候補の1つです。
- 雑柑の品種で、清見×オセオラと宮川早生の交配
- 12月上旬頃に収穫、果実は180g程度、糖度12-14度
- トゲが少しあるが、耐寒性があり、関東から九州で栽培可
- 2-3年で結実、1本でも実がなる
- 樹高2-2.5m、葉張り2-3mの常緑樹
- 風味はオレンジで、じょうのう膜が薄いため苦みが少ない
- かいよう病にやや弱い点に注意